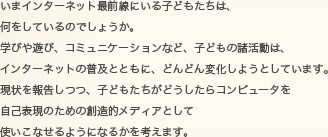本コンテンツは岩波書店 (1997/07)より発刊された「インターネットの子どもたち (今ここに生きる子ども) 」の内容を掲載しております。
掲載内容は執筆された時代背景を考慮し、書籍発行当時のままになっております。
コンテンツの利用・閲覧に関してはこちらをご覧下さい。
1.そもそもインターネットとは―同時代を生きるリァリティ
認知科学における新しい考え方

1996年3月9日、カリフォルニアで「ネット・デイ」と呼ばれるイベントが実施されました。いろいろなコンピュータ会社がもう使わなくなったコンピュータを放出し、近くの小学校、幼稚園、図書館など、まだコンピュータがないところにコンピュータをおいて、ネットワークにつないで、そこで子どもたちを含めていろんな人が世界中のデータにアクセスすることができるように、ケーブルを引き回し、ソフトを入れて、とにかく用意だけをしてあげよう、という壮大な企画でした。テレビでクリントンやゴアが、実際に厚手の断熱手袋をはめて、天井を剥がしてケーブルを引き回すところをニュースで放映していたので、覚えている方もおられるかもしれません。
その少し前、1996年2月8日には、27ヵ国から150人の写真家が1000人の協力者を得て、フィルム6000本以上、写真にして20万枚のデジタル・イメージをサンフランシスコに送り、それを80人のスタッフが整理し、文をつけてその日のうちに1 つの作品に仕上げてウェブ上で公開するというイベントがありました。すべて、「人々がこの日、コンピュータの入り込んできた今のこの時(これを「サイバースペース」と彼らは呼んでいます)をどう生きているか」を撮ったものです。「ジャーナリズム史上初めて」といわれる試みだったのだそうですが、それをその日のうちに「見に」行った人の数が400万人以上というのもスケールの大きな話です。この成果は今、24 hours in cyberspaceという本(Smolan, R. & Erwitt, J., "24 hours in cyberspace: Painting on the walls of the digital cave", Que Macmillan Publishers, 1996)とCD-ROMの形で見ることができます。
写真に写っているのは、アメリカ・インディアンの保留地にすむ美人のおばあさんのアップだったり、捕獲されて積み込まれたトラックの側面を壊そうとしている怒った象だったり、さまざまです。けれど、そのどれもがサイバースペースに「生きている」というのが作品を作った人たちの主張で、実際このおばあさんは自分たちの歴史や文化をウェブで公開しているのですし、捕獲された象は、発信器をつけた首輪を取り付けられたあともっと安全に生きていけそうな地域に放され、その後の行動が記録されて世界の象研究者にデータを送り続けることになります。同じ日(24時間という切り取られた時間枠の中)で、世界のあちこちではいろんな人がいろんなことをしていましたよ、というだけではありますが、写真を見ているだけでも、コンピュータという道具が生活に入り込んできた今という同時代を生きているということの広がりと不可解さを感じさせる仕上がりになっています。
世の中がこんなふうにしてどんどんコンピュータ・ネットワークでつながれていきます。それによって、私たちはこれまで考えられもしなかったほどいろいろな情報を、原則としては、すぐ手に入れることができるようになってきているのです。こういう情報のやり取りの変化が、「教え」とか「学び」と呼ばれる子どもたちと私たち大人たちとの関わりを変えていかないはずはありません。知とは何か、その知の研究の仕方、捉え方そのものも前の章で見てきたように変わってきつつあります。そういう変化に支えられて、学校という制度、学びに関する考え方が変わっていくのは時代の必然でしょう。
インターネットというもの、インターネットが負っているデータベースというものがまだ発展途上であるということは、むしろラッキーであるのかもしれません。今なら、そういうインターネットというシステム自体を変化していくものとしてとらえ、私たち大人がそれにどう立ち向かっていくか、というその姿そのものを子どもたちに見てもらい、そういう努力の中に子どもたちを一緒に巻き込んでいくことができるからです。でもだからこそ、変わってゆく媒体に対して、それをどう使ったらおもしろそうか、そもそもどんな媒体を作っていきたいのかについて、私たちは自分自身を柔軟にし、大胆かつはっきりした意見をもつ必要があると思います。
このようなことを頭におきながら、この章と次の章では、インターネットを実際教室に持ち込むために前準備として考えておいたほうがよさそうなことを挙げてみます。この章ではまず環境を整えたりそもそもネットで何をしようか決めなくてはならない時に考えておきたいことを取り上げます。次の章では実際教えるためにはどんな「心構え」が必要なのか、教えるという作業の意味をもう一度考え直すということをやってみたいと思います。
2.実践が成立する条件
コンピュータの環境

データをやり取りする、と簡単に言ってきましたが、実際どんな道具が必要で、どんな手順で何をしたら、どの程度のものが手にはいるのか実感が湧かないという方も いらっしゃることでしょう。通信のやり方そのものが、個々のハードやソフトも、また社会全体の基盤設備の整い方にしても、どんどん変わっていく時代ですから、その実情と変化についてはここでほんの少しだけ解説してみようとしても中途半端になるのでここでは触れません。けれど、教えや学びの絡んでくる場面で実際ここで考えてきたような実践が可能になるためには、少なくとも大前提として次の3つの条件が満たされる必要があります。
1つには、とにもかくにもネットワーク上で情報探しや編集や発信など知的な作業ができるコンピュータ環境が揃っていることです。周りを見回してみて、ネットワークをやっている人がまったく見当たらない、あるいはそういうことをやらせてくれそうな場所を思いもつかないという状況は、もうほとんどないでしょう。極端な話、コンピュータを扱っている電器店に行けば、インターネットと呼ばれる環境でどんな画面でどんな情報がとれるのか、見せてくれないところはありません。「100円で5分間だけ町角でインターネット」なんていうサービスも普及してくるでしょう。けれど、この話はハードの浸透度を反映しているだけで、先生や生徒が学校でとにかく使えるかという話とは別の話です。使えるかという話になると、ほんとうはソフトが使いやすいかとか、欲しい情報がすぐ見つかるかとかいう「使い勝手」の話もしなければいけないのですが、当面はまず何とか使える環境を整えるための支援が必要でしょう。まだ別ではありますが、ここのところが浸透しないことには話が始まりません。
ネットワーク作業ができる環境がすぐ手の届くところにあって、ただ使っていないだけ、ということなら、とにもかくにも工夫がいるのは使い方だから、できるだけ早くそのことに目を向けるようにすればいいでしょう。
そうでない場合には、当面の環境整備に相当の時間とエネルギーがかかることが、もっと問題にされる必要があります。人がすでにつないでくれたものを使う、という話と自分で一からつなぐという話はこれは相当に違う話であって、今は少なくとも学校という場に対する社会的なサポートが少なすぎる状態でしょう。
「ハードだけではだめだよね」という言い方をときどき耳にしますが、こう言えるためには、ハードが整っていなければどうにもなりません。特にネットワーキングが絡んできた場合、どこまでがハード的な問題かという境界をはっきりさせることはむずかしくて、コンピュータ同士がいつも安定してつながった状態にしておくための技術サポートまではぜひ必要です。本来はそのための専用の技術スタッフが「呼べばすぐ来てくれる」範囲にいるべきでしょう。残念ながら、今の日本ですと大学の情報系の学科でもそうなっているとは限らず、ネットワーク利用の研究をしているはずの人がネットワークの保守にも時間を割いているといった事情が多いものです。
まだまだ学校の先生が使いたいと思ったらどこかに電話をかけると1、2週間のうちに「つないでくれたものをすぐ使える」状態にしてくれる仕組みがある、というような状況にはなっていませんし、ましてや学校向けに「こういう情報はどこにあるでしょう」などの使い方のサポートを提供してくれる体制は、積極的な先生方が自分たちで協力し合って情報交換のためのグループを作っているなどの自発的なものを除いたらほとんどどこにもありません。ネットを学校で使ってどうなるという話を真面目に始めるなら、この辺の手当は早急に必要になります。ネットワーク活動をするための資金源がきちんとあることが大切なのは言うまでもありません。
通信する相手
2つ目は、通信する相手がいることです。国や組織が用意してくれる相手でもいいのですが、新しい実践であれば「やりたいこと」に賛同してくれる相手が見つかるかどうかが、やって楽しいかどうかに大きく響いてきます。本来ネットはいろいろな興味や関心を持った人たちがたくさん集まってくるところですから、同じ話をしたい人を見つけやすくてよさそうなものなのに、学校という活動時間やスケジュールの決まったところで相手を探すとなると、けっこう話がむずかしくなります。
国際的にネットを利用したい場合、端的には、日本の学校は4月始まりでアメリカの学校は9月始まりなどという一見何でもなさそうな違いがネックになります。ネットワークとは情報源なのですから、行ってそこにある情報をとってくればいいんじゃないの、という考え方があるかもしれませんが、情報の裏にはその情報をそこにそういう形で置いた人がいます。情報の整理や作り替えが問題になるときは、遅かれ早かれその人とのやり取りが必要になってきます。整理したり作り替えたりした結果を一緒に検討するためにも、いろいろな見方ができる相手が必要です。
2つ目の問題に付随して、国際的な通信を取り込もうと思ったら、言語がネックになります。これについては、今の翻訳ソフトの改良をまつ、などというのんきなことでは対処できないだろうと思います。ただ私は、言語がネックになるからあきらめるというのではなくて、言語をできるだけネックにしない方法を考えていくべきではないか、という気がしています。1つは、テーマ、領域に特化した辞書の整備が相当役に立つはずです。原語を生かしたまま、必要な辞書引きがすませてあるだけで、相当意味を取ることができるでしょう。話し合っている内容が特定のものであればあるほど、この辞書引きの効果は大きくなります。特定の話題に限定した辞書引きであれば、これは機械でも相当のことができますし、最近ではこういう辞書の作り方も研究されるようになってきました。
もう1つは、言語によらないコミュニケーションの手段を最大限に利用することです。たとえば、第一章の冒頭で、南中時の1メートルの棒の影の長さを交換する例を挙げましたが、あの時やり取りされたデータは数字です。何をやり取りするのかについての合意がきちんとできあがってさえいれば、複雑な文章をやり取りせずに授業に使える材料をやり取りすることは十分可能です。この2つのやり方はいずれも、狙いのはっきりしたプロジェクトをベースにしたやり取りのほうが、「お元気ですか」「はい、元気です」的な一見取りつきやすそうな、しかし内容の漠然としたコミュニケーションよりやりやすいことを示しています。
もう1つ言語のことに関して付け加えておくと、私たちはネットワーク利用を始めた当初から、ネットによって教室の中に多言語使用状況を作り出すことそのものに教育的な価値があるのではないかと考えてきました。日本でも海外から帰国してくる学生生徒が増えています。ところが、彼らが海外で身につけてきた言語や文化についての実践的な知識が教室の中で実質的に役に立つ機会を作ることは案外むずかしいと聞いています。ネットの上での活動においては、彼らの強みが生かされる場ができる可能性があります。メキシコとイスラエルの間での実践で実際に試してみたところ、一部の学生の負担が大きくなりすぎてしまってうまくいかないということもありましたが、今後の課題となるでしょう。
やりたいことがあるか

3つ目は、やりたいことがほんとうにあるかどうか、言い換えれば先生や子どもたちがネットを使ってやりたいことがあるか、やりたいことを思いつく下地があるか、「何をやろうかな」「何をやったら楽しいかな」を考えるエネルギー、余裕があるかどうか、ということです。3つの前提条件の中では、たぶんこれが一番大事です。
ネット上のメッセージのやり取りと聞くと「手紙のやり取り」が連想され、知らない人同士の手紙のやり取りと聞くと「ペン・パル」が連想されるせいか、ネットがつながるとまずは自己紹介という実践が多いようです。けれど、自己紹介は、たとえば前に出した南中時の1メートルの棒の影の長さを伝えることなどに比べてむずかしいのです。自己紹介は、「相手の状態をある程度理解したうえでの自分の長所の紹介」というようなもので、もともとうまくやるには高度な会話テクニックが必要なものですし、話題が決まっていなくて何について話してもいいとなるとかえって話しにくいというのは誰でも経験していることです。これに対して、どういうデータをやり取りするかがあらかじめ決められているプロジェクト形式でのデータのやり取りは、少なくとも何を送ればいいかがはっきりしている分だけ、取り扱いやすいと言えます。「ペン・パル」とのやり取りは、ある程度ネットワーク活動に慣れてからやったほうが実りが多い課題ではないかと考えます。
ネットを教育に利用してみたという経験そのものがあちこちに相当蓄積されてくるようになってきましたから、プロジェクト案についてもまずは他の人がこれまでどんなことをやってきたのかを調べることができます。この本の後の章でも、私たちが経験してきたことや主にアメリカで有名な大きなプロジェクトのいくつかについて簡単に触れますが、取り上げられてきたテーマは驚くほど多岐にわたるものの、案外同じようなプロジェクトが繰り返し扱われています。このような有名どころのテーマの中には、これまでのやり取りの結果が一種のデータベースになって利用できるようになっているところもあります。
ただ、先生がこれはおもしろそう、と飛びついたテーマがいつも必ず成功するとは限らないことも、ネットワーク活動のおもしろいところではあるでしょう。私たちの経験した失敗談を1つ披露しますと、大学生相手の多言語教育のテーマで、Unique Universal Projectというものを考えたことがあります。参加各国の間で、それぞれ、これこそは自分たちの文化に特有、つまりユニークだと思えるものと、反対にこれはどこの文化でも見られるユニバーサルな現象だろうと考えられるものを挙げる、という一種のゲームを考えました。このゲームでは、ユニークだとして挙げたものが他の文化に本当になければ1点、同じようにどこの文化にもあるはずとして挙げた事柄が実際他の国にもあればやはり1点、のように点数を競うことになっており、このようなゲーム性もこの活動を活発にする原因の1つとなるはずでした。
実際、「こういうことをやってみない?」と持ちかけたときの学生の反応はよかったのです。ところが実際に少しやってみるとすぐ分かったのですが、これはとてもむずかしいプロジェクトでした。たとえば日本の大学生の普通の英語力では無理でした。英検準二級から二級程度では対処できないのです。どこにでもありそうなことはまだいいのですが、日本特有と考えられる習慣とか現象を、そもそもことばできちんと相手に伝えようとすると、これはとてもむずかしいことになってしまいました。
相手の知らなそうなこと、相手とは共通の基盤がないことをことばで伝えようというのですから、むずかしくて当然でしょう。だからといって、どこの文化でもありそうでいて、しかし現象として日本特有というようなものは、今度は考えつくことがむずかしいということになります。日本の学生はずいぶんと自信を持って「日本の大学生は勉強しない」というものを日本のユニークな点として挙げたのですが、これにはイスラエルからもアメリカからも、「え? こっちの大学生もあんまり勉強しないけど?」という答えが返ってきて得点することができませんでした。
結局、「ネットで何をやろうかな」と考えるとき、一番の拠り所になるのは先生の「何を教えたいか」であり、生徒の「何を知りたいか」だろうと思います。日頃からの好奇心がものをいうところでしょう。こういう日頃の好奇心を枯渇させないようにしていくことにはけっこうエネルギーがいります。ネットワークが教室で生きるためには、先生も生徒も今より少し暇になって、「これから何がやりたいか」を考える余裕があることが一番大切なことかもしれません。
3.参考例はいろいろある
教室の中の小さなネットワークに学ぶ

子どもたち同士がやっている教室の中の活動をつないで小さなネットワークを作って、1人の子どもあるいは1つのグループが調べて分かったことを、他のグループや他の子どもたちにも分かるようにするなどの、出発点としてはとても大事な実践も少しずつその成果が報告されるようになってきました。
こういう実践例の1つとして聞いた話に、「互いのノートにリンクを自由に張らせたら、それだけでみんなの勉強する意欲が湧きました」とか、「自分の調べたことが他の人に役に立つ、そう気づいたときに子どもたちはとても活発になります」という報告がありました。子どもは伝えたいから学ぶはずだ、という考え方から見れば、それはあまりにも当然な話であるように聞こえます。でも、これだけ単純なことでも、これまではやりにくかったことだし、それだけにその効果がちゃんと確かめられたことはありません。もしこれが本当ならば、つまり、ネットワークが教室に導入されて子どもたちが素直に「人に伝えたいから学ぶ」という体験をすることができるだけで「学びが変わる」なら、ネットワークの持っている力はずいぶんと大きいのではないでしょうか。
こういう電子的な共同作業の場を教室の中に作りたいなら、「他山の石」にするとよさそうな実践例が実はすでにあります。みんなが必要な情報をネットワーク化した環境でどう使ったらうまくいくか、うまくいかない場合はどうしたらいいか、という実験は、学校の外の実社会の会社や大学など研究環境のなかではすでにやられていて、ずいぶん失敗例もあります。そういうところの経験から、学べるものは学んで利用するのが賢いだろうと思います。
たとえば、「調べて分かったことをやり取りする」といっても、ある特定の相手にだけ分かるように伝えればいいのか、もっと誰でも見たければ見られるようにある程度公開したほうがいいのか、などは工夫のしどころです。公開するのがいいかどうかは、当然内容にもよります。ある子どもが調べたことを他の子どもたちにも見えるようにする、そのことはいいとしましょう。これを出発点にするとして、一緒に仕事をしているとだんだん「調べた結果分かったこと」だけではなく、誰が、何を、どんな具合に調べているのか、それに対して自分たちは何をしたらよさそうか、などのいわば「調べ方」そのもの、仕事の進め方そのものの調整が必要になってきます。教えてもらうだけではなくて、「ここが知りたいから誰か調べてくれ」とか「あそこはどう進んでいるのか教えてくれ」というようなやり取りが必然的に出てくるのです。
こうなってきた時、こういうやり取りは、実はみんなに見えたほうが全体として仕事がやりやすいことが知られています。電子メイルといった基本的に個人と個人のやり取りを想定しているテクノロジーより、ここは、メイリングリストとか電子掲示板か何か、あるいはもうコンピュータからはいったん離れて教室の壁にみんながリクエスト・カードを貼り出す、といった方法のほうが効果が大きいかもしれません。こういうことは、早めにネットワークを導入してみた会社などでは知られていて、いろいろなことが試されてもいます。ネットワーク化されて、共同の作業というものがどういうところでどんなふうにやりやすくなってきたのか、あるいはやりにくくなってきたのか、学校の先生たちが世の中の経験から学べることも少なくはないはずです。
プライベートな空間と共有する空間
ついでにこういう話をもう1つしますと、一緒に仕事をしているとき、互いにやっていることをどこまでどう見せるか、というのはずいぶんと微妙な問題です。コンピュータ・ネットワーク上ですべての人のやったことがすべて他の人にも利用可能になることがベスト、ということはけっしてないようです。人間誰でも、自分がやっていること、特に今苦労して考えている真っ最中の「大事なこと」はまだそう簡単には人に教えたくない、ということがあります。そういうプライベートな空間と、みんなと一緒にものごとを考えていくための空間とは、できるなら分けておいて、しかも簡単に行き来できるほうがよいのです。
人が一緒に仕事をするためのコンピュータ・システムが研究され始めたころには、とにかく何でもみんなが共有できることがすてきなのだ、というシステムもありました。そういうシステムの中には、情報をたくさんため込んでおく余裕もいるし、いろいろな情報をいっぺんに表示できる大きな画面も欲しいし、などなどの理由でとんでもなく高価なものもありました。
ところが、実際使ってみると、みんなと一緒に新しい製品の企画などをやっている最中に突然、今の企画とは直接関係がないけれど将来役に立ちそうなアイディアが浮かんだりすることもあります。そういうとき、そのアイディアを、みんなにも見えてしまうところに書き留めることには抵抗があります。こんな経験が積み重ねられていって、最近の共用システムではたいてい、みんなで一緒に仕事をするための場所と、自分1人で仕事をするための場所とを分けて、どちらも別々にとっておくことができるようになっています。
今までどうなっていたのかを考えてみますと、みんなたいてい自分用のノートとか、メモ書き用の手帳などを個別に使っていました。それでは記録がばらばらになって不便だ、という面と同時に、そこには個人が他の人と一緒にいても隠れて1人だけで仕事ができる空間があったと考えることができます。電子化すると、何でもファイルにして取っておくことができて便利だからといって、以前使っていたノートのいいところまでなくしてしまう必要はないということでしょう。
使えるシステムへの試み

こういう話も、会社の話として聞いてもらえれば自然な話でしょう。学校でも、グループ作業がいろいろ取り入れられていると思いますが、それを、コンピュータを使ってやろうというときには、こういう1人1人の個人の仕事への配慮が大事になってくると思います。
学校のような、本来もっと人間1人1人の着想が大事にされなくてはならない世界であれば、なおさらのことでしょう。仕事の場よりもっと生徒1人1人のプライバシーを守ることができるシステムが必要になっていいと思います。先生がのぞいて見ることのできない生徒同士のやり取りとか、生徒が先生以外の学外の誰かからもらった情報とか、生徒が今はまだそっと1人のものにしておきたいウェブのサイトとか、これまで教室では建て前として存在が認められていなかったような生徒の「個人情報」を先生が尊重することの必要性などという問題が出てくる可能性もあるかもしれません。
会社ベースで行われてきたコンピュータによる協調作業支援システムの開発研究のなかにはこれまでの常識を見直させるようなものも出てきていて、学校への応用を考えると十分刺激的というものも少なくありません。
1つだけ例をあげますと、サン・マイクロシステムズという会社の研究施設で、外から人を呼んで来て講演してもらう際に、講演者には小さな部屋で数人を相手に講演してもらい、その様子を施設中の各研究室のワークステーションから見られるようにした、というものがあります。講演の日程が決まると案内が流れてきますので、聞きたいと思う人は登録しておきます。講演の時間になると、登録した人の研究室にあるワークステーションに講演用の窓が開いて、講演者の使うOHP(講義や発表会で使うプロジェクター)用資料などと講演の様子を見ることができます。講演者はネットワークを使って、部屋で見ているはずの人の意見を聞くこともできますし、聞いている人は「拍手ボタン」を押して講演者にエールを送ったり、「質問ボタン」を押しておいて指名されたら質問したりすることもできます。
このシステムの出発点は忙しい研究者が自分の仕事をしながらでも講演が聞けたら、まったく聞けないよりはいいよね、という着想だったそうですが、実際このシステムに慣れてくると、人々は、数人ずつある1人の研究室に集まって、講演者がしゃべっているあいだに受け手同士でも会話をしながら講演を聞くようになったとのことです。人が話しているあいだに聞き手同士でも意見交換するというのは、これまでの場所を共有した講演では物理的になかなかやりにくいことだったわけですから、こういう受け手の態度は言ってみれば常識破りです。けれど、実際そのほうが楽しいし有益だと感じる研究者が多いのだそうです。
授業にもそういう側面、つまり学生同士がコメントしながら聞けたら内容についてもっといろいろ考えるヒントが出てきて結果としては授業がよりおもしろくなり、深く学べるという側面があるのかもしれません。今の自分の大学での講義を思い返してみると、「えー、でもそんなシステムで講義したら誰も聞いてくれないよ」という気もしますが、そこで誰も聞いてくれそうもないならそれは当然講義の質の低さのせいでもあるでしょう。そういうシステムがあるなら、そこで学生を学生同士の真剣な議論に引き込むような講義をしてみたい、とも感じます。少なくともこういう実例を知ると、それにあわせて自分の今の講義のどこをどんなふうに変えたらもっと良くなりそうか、考えさせられることだけは確かです。