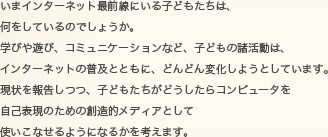本コンテンツは岩波書店 (1997/07)より発刊された「インターネットの子どもたち (今ここに生きる子ども) 」の内容を掲載しております。
掲載内容は執筆された時代背景を考慮し、書籍発行当時のままになっております。
コンテンツの利用・閲覧に関してはこちらをご覧下さい。
1.「学ぶ」という活動の見直し
認知科学における新しい考え方

「教育」とか「学び」と呼ばれる認知活動は、そもそもどんなふうにして起きるものなのでしょうか。情報化を迎えるこの社会の中で、子どもたちをインターネットへ誘うことを考えるなら、まずそういう原点から考え直さなくてはならないところもあるでしょう。もちろん、今私たちは、大人が知っていることをそのままことばで説明してやれば子どもも大人と同じようにものが分かるようになる、などとは思っていません。それどころか、「認知科学」と呼ばれる人の思考過程や判断の過程を考える研究分野の中では、大人であっても、頭の中にプログラムを持っていてどのような場面でもそのプログラムでできることを正確に再現することができるというふうには考えていないのです。
実際人間というものは、何を知っているか、どんなことを今まで覚えてきたか、というだけではなくて、「今、ここ」で何をしたいと思っているか、周りがどんなところか、周りに何があるか、周りにどんな人がいてどのような手助けを受けることができるか、「今、ここ」にいたるまでにどんな経験をしてきて「今、ここ」がその経験のなかのどれと一番似ていそうだと判断しているか、という今、その場の状況に大きく依存して、できること、やり方が変わってしまうのです。そちらのほうがむしろ自然な人間だ、と考えられています。反対の言い方をすれば、人はそのようにして、過去の経験を生かしつつ「今、ここ」の外の世界にあるもの(道具であるとか、他人であるとか)を上手に使うことができるから有能なのだ、というふうに考えられています。
たとえば、折り紙をわたされて、「この折り紙の2/3の3/4を切り取ってくれません?」と頼まれたとしてみましょう。あなたは何をするでしょう? 分数の計算?やってみていただくと分かりますが、答えは1/2になります。1/2を切り取るのであれば、計算すれば話は簡単、と思われるかもしれませんが、実際この問いをあちこちで人にしてみたところ、計算する人は10人に一人くらいしかいませんでした。たいていの人は、直接紙を折って答えを出そうとします(これについては、筆者と白水、益川の三人で英文の論文を執筆中)。三等分は折りにくいですが、何とか折ります。そしてできた2/3の部分について、またこれもそこを四等分するような折り方を工夫して2/3の3/4を求めてくれるのです。つまり、小学校で十分練習問題をやっていても、折り紙があれば人は計算しなくてもいい、そうやって外の世界にあるものを、その場の目的に合わせて上手に使うことがむしろ人間の知性の現われなのではないか、と考えてみることができるでしょう。人間の知とは何かについての考え方が、頭の中ですばやく計算できることといったものから、経験を生かし、外の世界にある道具(折り紙など)をうまく使って求められている答えを引き出すこと、といった見方に変わりつつあります。
人間の認知能力にこういう側面があることを強力に主張してきたのは、人を、その人が毎日普通に生活している場のなかで観察し、そこから人間の能力について考えてきた研究者の人たちで、その多くは文化人類学などのバックグラウンドをもっています。上の2/3の3/4の話も、ジーン・レイヴなどを中心としたそういった研究者が台所でした観察がもとになっています。
学校という文化の場に生きる力とは
その人たちによると、学校という生活場所はそれ自体が一つの文化であって、学校でよい成績を修めるということは、その文化への適応の程度がよくてその文化のなかで十分有能にふるまえることを意味します。だから、学校を卒業した後も、学校でやったように新しいことを次々覚える必要があったり、教えられたとおりのやり方で仕事をきちんとこなすことが求められたり、定期的に昇進試験があったりする社会でなら、学校で有能だった人がいきいきと生きられるでしょう。
ただ、そういう人たちが、学校ではあまり教えられないこと、奨励されないこともうまくやる、という保証はありません。むしろそういうことはできない、と考えたほうがいいような証拠があげられてきています(このあたりに興味のある方は『人はいかに学ぶか』(稲垣佳世子・波多野誼余夫、中公新書、1989年)、『日常生活の認知行動』(ジーン・レイヴ、無藤隆他訳、新曜社、1995年)などを読んでみてください)。
学校で奨励しないようなこと、暴力だとか、セックスだとか、ドラッグだとか、そんなものに若い人が染まらないほうがいいに決まっている、という範囲でならこの話はこれでいいのかもしれません。けれど、今学校であまり教えないことのなかに、たとえば与えられた枠をはずれるとか、これまで誰も試したことのない問題に取り組むとか、これまでのやり方を大幅に作り替えてみるとか、もうけっこう成果があがると言われている定評のある方法をわざわざ壊して作り替えようとしてみるとか、そういうたぐいの、これからの世の中でいままでよりもっと大切になるだろうと感じられていることが含まれていないでしょうか。含まれているのだとすると、レイヴたちの言うことは「学校ではそういうたとえば創造性と呼ばれるような能力はあんまり身につかないよ」という警告ともとれるのです。
人間の認知能力を研究している多くの研究者、認知科学者と呼ばれる人たちが、強度の差はあれ、レイヴたちのこのような考え方を支持しています。人間がこのようなものでなかったら、洗練された計算の速いプログラムを埋め込んだ人工知能がもうすでにさまざまな場所で活躍してくれていていいはずだったとも考えられるのですが、そうはなりませんでした。洗練されたプログラムを、人工知能が実際使われるであろう現実の場所にある物や人、特にそれらの変化に対して十分適応的に作ることが今のところまだできないからです。
「言われたとおりにすること」でテストにいい点が取れるなら、いい点を取るプログラムを作ることはむずかしくないでしょう。困るのは、人の有能さが、言われたとおりにできるかどうかでは決まらないというところです。人は、2/3の3/4を計算用紙の上で計算するのが適切だと判断すればそうするし、折り紙の上で折ってしまうほうがきれいで速いと思えば計算しないですませます。
こういう場への適応力が、人間の有能さの本質でしょう。学校は、人の有能さを育てるところですから、子どもの頭の中に「いつでも分数の掛け算を絶対間違えずに速くできる」プログラムを作りたいのではなくて、その場に与えられた状況を最大限に利用するにはどうしたらいいかが苦労せずに分かる適応力を目指したいはずだと思います。今の認知研究、教育実践研究では、そういう人の場への適応力の育成を目指すことそのものが、インターネットを教育に利用したいという発想を支えているところがあります。なぜそういう話になるのかをもう少し解説させてください。
2.知識を獲得することの意味を問う

教育というものは、ある一つの道を極めた人が、自分できちんと整理をつけて分かっていることというものを、まだ分かっていない人に少しずつかみ砕いて分かりやすく教えていくもの、そういうイメージが私たちの中にまだあるかもしれません。しかし、今のような時代の中で2年後、5年後、10年後に、今私たちが知っていると思っていることがそのままの形でまとまった知識として役に立つとはなかなか考えにくいでしょう。
「いや、そのままの形で役に立つか立たないかが問題なのではない。対象は何であっても、たとえば、今はまったく役に立たない言語の単語の羅列であったとしても、それを学ぶという経験そのものが役に立つのだ」とおっしゃるかもしれません。
しかし、前の節に紹介した認知科学の考え方は、そういう考え方が必ずしも成り立たないことを示しています。「実際には使われない、意味のない単語をたくさん覚える」訓練をすると、「実際には使われない、意味のない単語をたくさん覚える」能力が身につきます。しかもその能力は、その覚える努力をしたのに似た場面で、似たような材料を相手にしたときに最大限に発揮されるでしょう。しかしその能力が、たとえば互いに関連するしっかりした意味の構造をもったたくさんの単語、たとえば貿易に関連した法律条項と具体的な判決事例と現在自分がかかわっているたくさんの商品や顧客についての事実を覚えるのに役に立つかというと、少なくとも認知科学研究がなされてきた範囲では答えは否定的です。
今の教育に求められることは、私たちが完成した知識だと思っていることをかみ砕いて少しずつ子どもたちの中に移植していくことではないのではないでしょうか。それよりも、そういう知識そのものを私たち自身がどうやって膨らませ、育て、作り替えていくかというその私たち自身の知的な営み、それをどうやってやるのかを、子どもたちと一緒に体験しながら伝えていくことなのではないでしょうか。これから必要になる新しい知識を作り出すためにこれまで積み上げられてきた知識をうまく活用する、そういうことのできる力がこれからますます必要になってくるような気がします。
ずいぶん抽象的ではありますが、そういう力ならわたし自身けっこう真剣に身につけたいと思っています。きっと子どもも含めた他の人たちに一緒に身につけてもらってもそう損をさせることはないでしょう(少なくとも一緒に学ぼうという人たちに、なぜそれを学ぶとよさそうかは説明できます)。インターネットは、そういう力を身につけるために必要な道具の一つとして捉えられますから、今、認知科学などの分野から教育を研究しようとする人たちにとっておもしろい研究テーマなのだと思います。
3.人間関係と知識
ネットワークとしての知
インターネットがどうして知識の有効活用と新しい知識の生成のための学習道具になるのか、その話にゆく前にもう少しだけ、知をどういうものとして考えたらいいのかについての話を続けたいと思います。ネットでつながっている情報というものは、原理的には、いつでもどこからでも取り出せることになっています。言い換えれば、ネットワークという道具がこういう特殊な知のあり方を許容するようになってきています。人が持っている知というものも、一人の頭の中に何がどれだけ詰め込まれているかでその質が決まるのではなくて、いつどんなときにどれだけ引き出せるか、引き出してきた結果がどれだけ他の人の知と相互作用を起こしてよりよく変われるか、というような側面が大事だということになってきつつあります。こういう「知のネットワーク的な見方」がなされるようになってきたのに従って、この段落の冒頭の問題が問題として受け入れられるようになってきたとも言えます。
知が他人の知と相互作用を起こしてよりよく変わるというと、むずかしいことのように聞こえるかもしれませんが、実際これはどこでも起こっていることです。子どもたちがどうやってことばをしゃべるようになっていくのかを考えるときに、大人とのことばによる実際のやり取りの手助けなしに、「ことばというのはこういうふうにしゃべるものですよ」というような説明だけを親から聞いてそれで子どもが勝手にしゃべれるようになる、と思っている人はいないでしょう。実際、テレビで話されることば、親がかけることば、友だち同士遊びながら試してみて身につけていくことば、そういうものを取り込んで私たちの言語能力というものはできあがっています。子どもは、周りから受け取るいろいろなインプットを自分で整理して、自分でその中に規則を見つけて使える知にしているのだと考えられます。
そしてその規則に従って実際使ってみて、当たっていればその規則に自信を持つし、「そう言うんじゃないよ、こんなふうに言うんだよ」と直されればそれに従って変えていく、ことばをしゃべる知力はそんなものとして育ってくると思われています。私たちは実際、多くのことをこれと同じような方法で、人からの手助けをだんだん自分のものにしながら身につけていると考えられるのではないでしょうか。
最近接領域と子どもの成長

ソビエトの心理学者にヴィゴツキーという人がいましたが、この人は人の認知的な発達を、典型的に社会的なもの、つまり他人からの手助けを徐々に内化する過程だ、と考えました。私たちもみなそうでずが、子どもにはまず、一人でできることというものがあります。しかし子どもができるのはそれだけではありません。その子は、手助けをしてもらえば、一人でできることよりももう少したくさんいろんなことができるものです。
平らなところをよちよち歩きでやっと歩けるようになった子どもが坂道に差しかかったとします。その坂道を子どもがのぼり損ねているとすると、そばにいる大人はどうするでしょう。その子にそっと手を差し出して、子どもの手を取って引いてやって、つまり手助けをして坂道をのぼらせようとするのではないでしょうか。子どもの側から言えば、この子どもは、手助けを得てその坂道をのぼることができます。一人で立って歩けることはもちろんこの子どもの能力ですが、大人に手を添えてもらえば坂道をのぼることができるのなら、それもこの子どもの一つの能力です。おそらく近いうちに、この子は、大人に手を添えてもらわなくても坂道を一人でのばれるようになるでしょう。そして、そうなったら今度はまた別の手助けをしてもらって別のことができるようになってゆくでしょう。
ヴィゴツキーは、子どもが発達するのには発達の最近接領域がある、というふうに考えました。自分一人でできること、それの上に発達の最近接領域として人に手助けしてもらえればできることの領域がある、というわけです。そのような領域をなぜ最近接領域と呼ぶかというと、ヴィゴツキーの考え方によれば、その領域の中に含まれることが、その子どもが次にできるようになる可能性の最も高いことがらだと考えられるからです。つまり発達する可能性の最も高い、発達に最も近接した能力の領域ということになります。今手助けしてもらえばできることがだんだん一人でできることに置き換わって、坂道をやっとのぼれるだけだった子どもがだんだん、走ることができるようになったり、ブランコを一人でこげるようになったりしてゆくのでしょう。子どもが発達するに従って、最近接領域そのものも変化してゆくと考えられるわけです。
認知的な能力にも同じことが言えます。ことばの獲得もまさにそうでずし、数が数えられるようになった子どもたちが母親や父親と一緒に数を唱えているうちに数えられる数をどんどん増やしていくなど、子どもたちは始め手助けしてもらってしかできなかったことをだんだん自分一人でできるようになっていきます。
このような仕組みで子どもが発達していくのだと考えると、そこからはいろいろな推測をすることができます。子どもの目から見れば、手助けをしてもらってできるようになったこと、それを自分一人でできるようになって発達の階段をのぼっていく、というふうにも言えます。しかし、同じことを大人の側から見れば、これは子どもができるようになってほしいこと、こういうふうになってほしいと思える能力、そちらのほうに向かって手助けを提供するということになるでしょう。子どもがやってほしくないことを一人でやろうとしているとき、大人はそれを無視するかもしれません。そのような、手助けを与えないということによって子どもがそちらの方向に伸びるのを防ぐ、というような働きも、発達の最近接領域は持っていると考えられます。
こういう手助けを、私たち大人は意識的にも無意識的にもしたりしなかったりしていると考えられます。極端なことを言えば、私たちはみな、人が喜んでくれれば頑張りたくなるし、いやな顔をされれば気が引けます。だから、子どもがしたことににっこり笑ったり、しかめっ面をしたりする大人の反応そのものが手助けとして働きがちなのです。だとすると、私たちが何に価値を置いているか、何をいいと思い何をいやだと思っているか、何が好きで何が嫌いかなど、私たちの価値観そのものに基づいて、子どもの周りの発達の最近接領域が形成されている可能性があります。世の中がどんどん保守化しても不思議はない、とも言えるのです。
学校という環境
同じことを学校について考えてみましょう。周囲の大人たちの中で大切にされていること、それが子どもたちにとっての手助けの環境になるのだ、というふうに考えるなら、実際学校というのは多少奇妙なところだと言わざるをえません。とにかく大人の数と子どもの数がアンバランスです。小学校で、一人の先生が算数も、国語も、理科も、社会も、体育も音楽も教えている、というような場合、先生は教え方のプロではあるかもしれませんが、それらの分野の内容についてすべてプロ級であるということは考えにくいでしょう。国文科を出た小学校の先生が体育を教えなければいけないこともあるでしょうし、ピアノが大好きで物理が専攻だった先生が社会科を教え、道徳の授業もするということもあるかもしれません。
子どもたちが先生にどんなことを褒めてもらい、どのような手助けを得られるかは、先生となる人がそのテーマにどれほど興味を持っているか、どれほど精通しているかと密接に関わりあっています。算数、数学が大好きな先生は、子どもが数を数えるおもしろいやり方を見つけたときに、そこに数学的な才能を見て取って、新しい教具を考えてその子が数学的に伸びていく手助けを考えつくことができるかもしれません。数学よりは国文が得意という先生であれば、同じような行動をとった子どもに対して、同じような手助けを考えつくことはむずかしいのではないでしょうか。それよりも、その子の数の数え方のおもしろさというもののなかに、詩の芽を見て、それを文章にしていくことや文字で表わしていくことのほうに手助けを与えるかもしれません。
先生が与えてくれる手助けを生かしたり無視したりしながら、子どもは成長していくのでしょう。ただ、こんな簡単な例を考えてみただけでも、子どもを見る目、手助けを出せる手は、どちらも数が多いほうがおもしろいのではないかという気がします。学校がそういう意味で、子どもを多角的に捉え、多面的に支えようとする場であったというケースを私はあまり間いたことがありません。何よりもまず、学校という構造、先生一人に生徒がたくさんというあり方そのものが、物理的にも制度的にもそのような実践に不向きだったためではないでしょうか。
いずれにせよ、まず子ども一人一人の興味や関心に対応した質の良い最近接領域を確保するためには、その一つ一つの興味や関心に対応できるだけの大人の側のヴァリエーションが必要だろうと思います。そのためには大人がたくさんいたほうが便利です。そういう人がたくさん見つかるためには、やり取りが時間や空間に制約されにくいネットワークが有効です。そういうやり取りを保証してくれるようなネットワークの使われ方を開発していくべきなのだと思います。
4.情報化時代に求められる能力
情報はどこかにある
情報化社会といっても知りたいことがほんの少し速く簡単に手に入るようになっただけのこと、という人もいますが、このほんの少しの差で「覚えておくこと」の価値などは大きく変わる可能性があります。
何かを空で覚えていることというのは、昔、といっても私の学生時代くらいまでさかのぼっただけでさえ、とても大切なことでした。試験のときに、教科書のどこに出ていたかまでは思い出せたけれども、その内容が思い出せなくて、悔しい思いをしたものです。そんな思いは私たちみんなが持っているに違いありません。そのせいか、今でもやっぱり日常生活の中で何か情報がないと気づいたとき、一瞬、覚えていればよかったなと思います。けれども、次の瞬間には、あれ、どこかにあるはずだ、探してみようかということになって、本棚にではなく机の上のコンピュータに手が伸びるのが今では普通になってきています。捜し物が必ず見つかる、というわけではもちろんないのですが。
家でも職場でも、身の回りのコンピュータがどれもネットワークにつながっていて、情報はどこかにあるはずだ、というふうに世の中が変わったとき、情報を知っていること、今ここで私があなたに伝えられることそのものは、そんなに価値がなくなってくるのではないでしょうか。情報はどこかにある、問題は情報が多すぎることなのだ、そんなふうに私たちは思うようになり始めています。
子どもたちを取り巻く社会でも同じことが言えるでしょう。これから先いつまでも、ある短い時間に教えてもらったことを、あるほんとうにごく短いテスト時間という時間の中で思い出せるかどうかで子どもの価値づけをするという習慣が続いていくとは思えません。情報はどこかにあるのです。情報を探すこと、情報が探し出せることのほうが大事になる世の中がもうすぐ来ます。情報はどこかにあるのだから、とにかく頭に詰め込んで覚えておくことは大切ではなくなるでしょう。しかも情報のなかには変わるものもありますから、昨日の情報より今日の情報のほうがいい、ということもありえます。そのことによって、これからじわじわと、学ばなければいけないことの質が変わるのだ、と考えてみる必要があるでしょう。
発見したことを伝えるよろこび

認知科学という学問では、人は何か新しいことを発見すると、それを他人に伝えたいと思うものだ、と考えられています。なぜそのようなことがあるかというと、これはやはり、人間という種が社会的な存在として群を作って協力し合いながら自分たちより大きい動物を倒し、一人だけではコントロールすることのできない天災やさまざまな不便と戦って生き延びてきたその歴史と無縁ではないでしょう。
誰か一人の人が新しいことを見つけます。新しいたべものを見つけたというのでもいいし、今まで使っていた槍の矢尻を少し違った削り方にしてみたら今までよりも動物がうまく倒せることが分かったということでもいいのです。何か新しいことが起きた時、それが何かの利益に結び付くのであるならば特にそうでしょうが、これは仲間に伝えておいたほうがよさそうです。そうしておいたほうが、人間という種、今自分が仲間になっているそのグループの生存、生き残りの確率が増すと考えられます。人間は、自分たちが生き延びるために、分かったことは人に伝えるという認知的な性質を、進化の長い時間をかけて育ててきたのだ、と考えてみることもできるでしょう。
しかも、これもまた人の認知特性として、人は他の人にもっとよく分かってもらおうとするなかで自分自身の分かり方をだんだん深めてゆくものだ、ということも分かってきています。
こういう、知りたいとか、もっとよく分かりたいなどの人間に基本的に備わっていると考えられる傾向を認知的アージ(cognitive urge)と呼びます。アージは、たぶんそういうものが備わっていたほうが生存に都合がよかったと考えられるようなものごとの判断の仕方の傾向で、こわいものが出てきたらとにかく逃げ出したくなる、などもその一種だと考えられています。どうしてそういうものが身についたのかは推測の域を出ませんが、とにかくそういう基本的な性質が人間にはある、と考えるのです。
だとすると、人は、新しいことを見つけて周りの人に伝えてみんなで得をしたいから学ぶのだ、というそういう学びの原理が進化の結果として人間の中に潜んでいる可能性があるのではないでしょうか。分かったことは伝えたい、伝えるためにもっとよく分かりたい、それが人間の認知活動の一つの性質だとすると、子どもが自分でも何か新しいことを分かって人に伝えたいと思うような場面を設定することができれば、その中で、「分かりたい」「学びたい」という気持ちが育まれるのかもしれません。
伝えることが喜びなら、「人に知らせたら喜んでもらえそう!」、「伝える価値がありそう!」、「こんなこと私が初めて見つけたんじゃないかしら?」と思えるようなことなら何でも、見つけてうれしい、知ってうれしい、分かってうれしい、ということがあるのではないでしょうか。
こう考えてみると、「すでに先生のほうがよく分かっている」と子どもにも思えてしまうようなことを先生がいくら説明しても、子どもがそれを分かってまた誰かに教えられたらすごくうれしい、ということはなさそうです。だとすると、少し出来る子がかえって「何も教えてもらうことがなくて」学校がおもしろくなくなってしまったりする可能性すらあります。その子が一人で、初めて見つけたことでなければ、周りの人にわざわざ伝えたいとは思わないでしょう。
学校という「教え」のための機構がどうやって作られたか、それも人間が生き延びるためであったでしょうから、それはそれとしてどうやって形作られてきたか、その役割はどうやったら一番うまく働くのか、そのあたりのことはまたきちんと検証しなければなりません。けれど、その結果として現代の子どもたちが埋め込まれている「教室」という場面、先生が十分な準備をしたうえでなされる授業という形の中で起きるはずの「学び」が、子どもたちにとって少なくとも伝えたいから学ぶという気を起こさせるものではないのだとしたら、それは一種不幸なことでしょう。
コンピュータ化時代の大人

コンピュータ化していく社会の中で、私たち大人がどのようにしてコンピュータを使っていくのかにも、もちろん大人の価値観が反映されます。子どもたちはそれを見ながら大きくなっていくのでしょう。コンピュータ・ショップなどで、ときどき小さな子どもが一生懸命マウスを動かしているのを見ることがあります。棚の上でマウスを動かしながら、画面の上に何らかの変化が起きるのを熱心に見つめています。かつてどこかでその子が見つめていた大人が、やはり一生懸命おもしろそうにマウスを動かしていたのかもしれません。
大人が一生懸命やっていることを見つめ、大人に手を添えてもらってマウスを動かしたりしているうちに、子ども自身がマウスを動かして画面を変えていくように動機づけられていく、というのは自然なことの流れでしょう。たくさんの情報を操作する、そういう能力を大事にする大人の社会の価値観がありますから、そのような活動に興味を向けた子どもたちに対して私たちが手を差しのべている、というふうにも考えられるでしょう。そういうなかで、私たち自身がコンピュータをどんなふうに使っていくかを見ながら子どもたちが大きくなっていくのだとすれば、やはり私たち大人がインターネットにせよ何にせよ大量の情報をうまく使って、うまい使い方の方向に子どもたちを手助けすることができたほうが望ましいと思います。
ヴィゴツキーの言うことを真面目に考えるなら、大人はもっといろんなことを子どもと一緒にやるようにしたほうがいいのではないでしょうか。そういうなかで、大人がもっと積極的に、一種の覚悟を持って、子どもに何をやってほしくて何をやってほしくないのか、それはなぜなのかを伝えていける機会が必要なのかもしれません。子どもが背伸びして新聞を読もうとするとき、「新聞を読むのはまだ早いよ」と言うのか、記事を話題にして話し込むのか。新聞でなくて週刊誌だったらどうか。深夜のテレビ番組だったらどうか。手助けのできる側の人間が、ただ手助けをするだけではなくて、なぜ、どういうつもりで、どこまで手助けしようとしているのか、それについて手助けされる側と話し合ったりすることができたら、そこに形成される発達の最近接領域の質も変わってくるでしょう。
子どもが何かやってみたいと思うとき、少ない数の大人としか接触がなければ得られる手助けの種類や質にも限りがあります。もっといろいろな種類の手助けが、いろいろな形で得られれば、最近接領域そのものが変わってくる子どもだっているのではないでしょうか。発達の根本に、「手助けする/される」という人と人とのつながりがあるなら、そのようなつながりを提供できるインターネットに、人が発達するための道具としての役割がまわってくるでしょう。
言い換えれば、ネットを上手に使う大人が子どもの周りにたくさんいる必要があります。いままである程度うまくやってきたことのやり方を見せるだけでなく、こうやってなんだか日々変わっていく世の中で、昨日よりもう少しうまくものごとをやるにはどうしたらいいかとか、新しいおもしろいことはないかとか、大人が一生懸命やっている試みへの取り組み方そのものであっても、子どもに見せていけないということはないでしょう。大人がしている科学研究や技術開発といった社会を変える試みは、今はまだない手助けを自分たちで作り出しながら進んでいく方法なのだとも考えられます。
ネットワークの上で研究や開発の最先端情報を誰にでも公開していくということは、大人が自分たちのやっている科学研究や技術開発に子どもたちを巻き込んでいける可能性を開くことにもなりそうです。科学研究とか、技術開発とかそういう創造活動に長けているはずの大人が、でき上がった価値観に従って子どもに手助けをするだけでなく、自分たちが伸びていきたい方向に手助けを自分で作り出していくその方法そのものについて子どもに手助けしてやることができるようになるかもしれません。そうなることで、ネットワーク化した社会がつくる発達の最近接領域は、でき上がった価値を再構築するためだけではない手助けが埋め込まれた、これまでとは質の違ったものになっていく可能性があると思います。
情報を集め、発信する

まずは、情報がどこにあったか、どこへ行ったらその情報をもう一度見ることができるか、あるいはそれに関連したもっとよさそうな情報をどうやったら集めてくることができるか、情報の集め方がこれからは大切な力の一つになっていくでしょう。そして次にはそうやって集めてきた情報をどうするかが問題になりそうです。
まとめたり、整理したり、あるいは使い方に応じてちょっと作り替えたりすることが必要になってくるでしょう。ただし、ここでそのような活動が魅力的であり続けるためには、何か分かりたいことがあって、そのためにそうする、という形になっている必要があります。
情報を集めてきて、あたためて、そこから何かが分かるとします。そうするとそれは、新しく分かったことだから、他の人に伝えたいのです。他の人に伝えて、他の人が喜んでくれて、ああよかったなという感じがあれば、その先にまた進んでいこうという気になるでしょう。逆にそのような感じがなくて、でも自分は何か分かってきてほんとうにおもしろいんだ、ということになれば、これはほんとうに他人がまだ気づいてさえいないことなのかもしれませんから、これはどうしてもうまく人に伝えたくなるはずです。そうすると、情報の伝え方というのも自然と工夫されることになってくるでしょう。
こういう情報集めと情報伝えのための媒体としてインターネットをとらえてみたらどうでしょうか。教科書という限られた範囲に情報を限定して考えてきた昨日までに比べて、子どもがそういう作業の対象にできる情報の「量」が圧倒的に多くなってきています。情報がとにかくこわいほどたくさんあります。学校の先生にとっては、そういうたくさんの情報を相手に、どうやって集めて、どうやってあたためて、どうやって伝えていくのかが先生方一人一人にとってはまず問題でしょう。それをうまくやればおもしろいよ、ということを学校や先生が子どもに伝えることが、インターネットを教育に生かすことになると思っています。
ここで、まとめてみます。人の有能さは、今そこにあるものを上手に使ってその場その場で必要なことをなしとげ、他人から与えられる手助けをだんだん自分のものにして知識や技能をふくらませていくところにあります。言い換えれば他人の手助けは、意識的、無意識的に人がこれまで蓄積してきた知識や技能を受け継ぐ手伝いをしています。一方人は、そういう蓄積の上に新しいことを思いついたときには他人に伝えようとしますし、他人にも分かってもらえるよう自分で自分の考え方を磨くということをするようです。他人の存在は、最初はどれも個人の思いつきから始まる個人の「新しい考え方」が十分熟成するための試金石としての働きもすると考えられます。人の有能さ、知というものの本質がこういう社会的なものだとすると、今大人たちが活発に知の伝え合いや作り直し合いのために使っているネットワーク環境は、子どもたちにとっても知を身につけるための学びを引き起こす場所として十分期待が持てそうではありませんか。